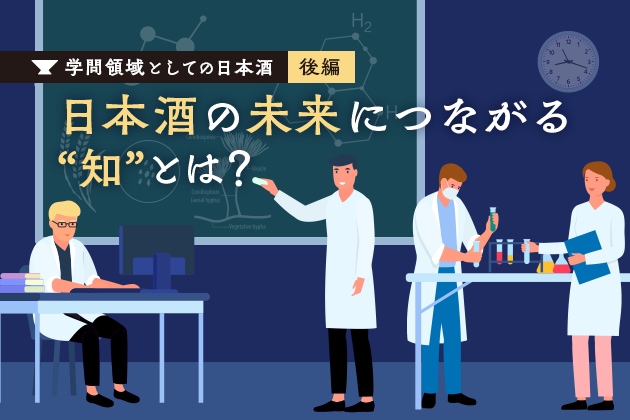
2025.07
29
日本酒の未来につながる“知”とは?:学問領域としての日本酒(後編)
これまで「日本酒の研究」というと、醸造学や農学が製造や原料について研究する理系(自然科学)分野が中心でした。ところが近年、日本酒をさらに多角的な学問の視点から捉えようとする新たな学問分野「日本酒学」が広がってきています。例えば、経済学や文学などの文系(人文社会科学)分野から日本酒を見ると、「お酒が持つ本当の価値とは?」といったテーマを掘り下げることも可能になります。
前編では、現在各地の大学で広がりつつあるこの新しい学問分野についてどのような取り組みがおこなわれているのか、概要を整理しました。
今回は、日本酒を複数の学問分野にまたがる“学際的”な視点で捉えることの意義を、実際の研究者へのインタビューや、世界の学際的な研究事例を通じて考察します。
さらに、こうした取り組みが単なる学問の探求にとどまらず、産業の現場が持つ「実践的な知」と結びつき、両者をさらに発展させるには何が必要なのか、実際に日本酒産業に関わりながら、日本酒学を専攻している著者自身の視点から提言します。
※当社はAmazonアソシエイト・プログラムに参加しており、本記事にはアフィリエイト広告リンクが含まれます。
経済学が明らかにする日本酒産業の構造と課題
『お酒の経済学』(中公新書)や『お酒はこれからどうなるか』(平凡社新書)などの著作を通して、経済学的観点から日本の酒類業界の課題を提起してきた一橋大学名誉教授の都留康(つる・つよし)先生。前編で紹介した日本酒学研究会の顧問も務めています。
「現在、日本酒に関する学問は醸造学が中心で、どのような社会経済的システムの中で生産・流通・消費されているのかという視点が欠けています」と指摘する都留先生。
「経済学の立場から見ると、日本酒には、企業組織や市場構造、バリューチェーン全体を含めた総合的な分析が足りていません。これは、自動車などほかの製品分野ではあたりまえにおこなわれてきたことです」
経済学から日本酒を読み解くと、どのようなことが見えてくるのでしょうか。
「例えば、日本酒の歴史において、明治期に生まれた軟水醸造法と速醸法は2大イノベーションであると言うことができます。軟水醸造法は、広島のような軟水地域でも酒造りを可能にしたことで地域間競争を生み、速醸酛は乳酸を人工的に投入することで製造時間を短縮し、生産工程の工業化・省力化を実現しました。いずれも単なる技術革新でとしてではなく、社会的・経済的影響を含めた評価をすべき技術です」
一例として都留先生が挙げるのが、経済学的な「価値」の捉え方です。経済学には、製品やブランドの価値を「機能的価値」 と 「意味的価値」に分けて評価する考え方があります。
「エアコンという製品の場合、従来は冷房機能だけを備えていましたが、暖房や除湿といったさまざまな機能が付け加えられたことで、機能的な優劣による『垂直的な差別化』が生まれました。
日本酒の場合、速醸酛が全国的に普及したのをきっかけに、味の均質化が進んだ結果として、近年は生酛や木桶などを用いた伝統製法への回帰が起きています。酒蔵が個性を出し、多様性を広げるこのような動きは『意味的価値』の追求であり、消費者の好みや価値観と結びつく『水平的な差別化』につながっています」
ほかにも、2023年にアメリカに醸造所をオープンした獺祭が、トヨタの現地生産化やキッコーマンの海外拠点設立と同等の戦略性を持つこと、現在の酒税法による参入規制については、自由な参入が可能な状況と比較する「カウンター・ファクチュアル(*)」的視点が必要であることを都留先生は解説します。
「人文社会科学系にあるのは『人間』の視点です。日本酒学を学問として確立するためには、経済学、社会学、歴史学などの研究者を増やすことが今後非常に重要になってくるでしょう」
*カウンター・ファクチュアル(反実仮想):実際には起こらなかった出来事を仮定して考える思考法。この場合は、「清酒製造免許が禁止されていなかったら日本酒業界はどのようになっていたか?」と仮説を立ててみること。
日本酒研究に必要な“文化のまなざし”
早稲田大学教授であり、「食と農の研究所」所長を務める福田育弘(ふくだ・いくひろ)先生は、「飲食表象論(飲食の文化学)」を専門に、ワインと日本酒を含む日本とフランスの比較文化研究をおこなっています。
「日本酒でも近年、ワインにならってペアリング(料理との組み合わせ)が謳われるようになってきていますが、フランスでワインを料理に一品ずつ組み合わせるようになったのは、実は19世紀中頃以降になってからなんです。かつては日本と同じように、料理はまとめて卓上に並べられていたのですが、ロシアの影響で温かいものを温かいうちに提供する方式が広がり、それにともなってそれぞれの料理にワインを組み合わせるようになりました。
このように、現在『伝統』とされているものでも、意外と歴史が浅い場合があります。比較文化の視点は、そうした事実を明らかにしてくれるんです」
福田先生がフランスでの生活を通して感じたのは、日本酒と料理のペアリングではアミノ酸による味の調和に重きが置かれる一方で、ワインは酸味によって口の中をリセットする機能が重視されるということ。こうした違いについて、「日本酒をワインの基準で評価すると、本来の価値が見落とされてしまうことがある」と指摘します。
「フランスの人々に日本酒のアミノ酸によるペアリングを提案しても、なかなか理解してもらいづらいことがあるように、海外に日本酒を輸出するときは、日本の価値観をそのまま持ち込むのではなく、現地の文化や市場の前提を理解することが必要です。
たとえば、フランスで実際に暮らしてみると、ワインはお酒というよりは発酵食品としての性格が強く、日本酒のように『酔うこと』を目的としていないことがよくわかります。ワインには酒税も課されていませんし、食卓に欠かせない液体という意味では、日本酒より『味噌汁』に近いと言えるかもしれません」
フランスにとってワインや食事は「国家アイデンティティに関わる重要な研究対象」であり、ワイン醸造学(Oenology)やブドウ栽培学(Viticulture)という独立した学問がある一方で、歴史学や地理学においての研究が充実していると教えてくれた福田先生。
「日本では酒類の研究が理系分野に偏重してきましたが、醸造学とは『誰もが安定した品質の酒を作る』ためのものであり、価値の高い酒は技術だけで再現できるものではありません。サステナビリティや自然派の文脈から、大量生産のためのテクノロジーが批判される現在、人間の技術、哲学的視点、社会的文脈といった要素が今後の研究における鍵となるでしょう。そうした意味で、文化人類学や歴史学など、広い視点から日本酒を捉える研究者が求められています」
産業に結びつく学際的アプローチの可能性
都留先生と福田先生のお話からは、日本酒学が実社会の課題を解決するためには、これまで足りなかった人文社会科学的な視点を取り入れていく必要があることがわかりました。さらに、ワインなど世界のほかの酒類に目を向けると、産業界のニーズに直結する取り組みとして、学部間を横断した複合的(学際的)な研究がなされていることがわかります。
(1) 気象学 × 経済学|気候変動とワインの持続可能性
英国ロンドンの「グランサム気候変動・環境研究所(Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment)」では、自然科学(気象・環境)と社会科学(経済学・政策学)の知見を持つ研究員たちが共同研究をおこなっています。
ケイト・エリザベス・ギャノンらが発表した研究論文「イギリスのワインセクターにおける気候変動への適応(Adaptation to climate change in the UK wine sector)」では、英国のワイン関連企業がどのように気候変動に適応しているかを、時間的な視点やバリューチェーン全体の観点から考察しています。
また、フランス・ボルドー大学ISVV(ブドウ・ワイン科学研究所)のナシディル・ルイアイらによる「ワインツーリズムはブドウ畑のエコロジー転換の新たな味方になるか?:ロワール渓谷を例に(L’œnotourisme, nouvel allié de la transition écologique au sein des vignobles ? Exemple en Val de Loire)」では、ワインツーリズムを活用することで、農家が生物多様性を守る活動を積極的に打ち出したり、消費者の環境配慮の意識が向上したりする可能性を探っています。
これらの研究は、ワイン業界全体での環境保護の取り組みを改善し、消費者を巻き込んだ企業のサステナビリティ対応を可能にします。
(2) 官能学 × 心理学|五感が変える味の体験
英国オックスフォード大学の実験心理学者チャールズ・スペンスは、人間の五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)が互いに影響し合う「クロスモーダル感覚」をもとに、ボトルの重さによってワインの価格が変化するか、照明・音楽によってワインの評価がどのように変わるか、開栓音が味覚にどのような影響を及ぼすかといった数多くの実験をおこなっています。
こうした研究成果は、ワインの生産者や販売者が顧客の体験を最大化するプロモーションを向上させるかもしれません。
参考:
- 「ワイン心理学:基礎と応用(Wine psychology: basic & applied)」
- 「多感覚環境がワイン飲用体験に及ぼす影響に関する大規模サンプル研究(A large sample study on the influence of the multisensory environment on the wine drinking experience)」
(3) 考古学×化学|遺物に残る成分から酒の起源を読み解く
ペンシルベニア大学博物館のパトリック・E・マクガヴァンらが「米国科学アカデミー紀要(PNAS:Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA)」に寄稿した「フランスにおけるブドウ栽培のはじまり(Beginning of viniculture in France)」は、南フランスのラッタラという古代の港湾遺跡で発見された「アンフォラ」という土器の壺などに残った有機物を化学分析した結果、ヨーロッパにおけるワイン文化の歴史の重要な基点を発見する研究となりました。
同様にして、米デラウェア州のクラフトビール醸造所ドッグフィッシュ・ヘッド・ブリュワリーは、マクガヴァンらの資料を参照し、「王様の耳はロバの耳」の寓話で有名なミダス王の墓から発見された2700年前の酒器の残留物の分析をもとにビールを醸造。このビール「ミダス・タッチ」は、アメリカのビール界の権威である「Great American Beer Festival (GABF)」のブロンズ賞をはじめ、コンテストやメディアで高い評価を受けました。
このように、学問領域を横断する柔軟性を持つことで、実際の産業で求められるより多様なテーマへのアプローチが可能になり、実社会の課題解決や個々の企業の戦略へとつなげられるのです。
現場とつながる日本酒学を、産学連携で育てる
特集「学問領域としての日本酒」では、まだ始まって間もない日本酒学という学問について、前編で現状の概要を説明し、後編で今後の指針となる「学際」というキーワードを掘り下げました。
メディアという立場から日本酒業界に関わってきた著者は、2023年に新潟大学大学院 博士前期課程に入学し、2025年現在は博士後期課程で日本酒学を専攻しています。私が本学に進学したのは、日本酒産業を持続的に発展させるためには、生産的な産学連携(場合によっては産官学連携)を追究する必要があると考えたからです。
メディアとして業界の課題を取り上げながら、個々のプレイヤーや企業の努力で実現できることには限界があることを痛感していました。そして、その解決策のひとつとして、企業が抱える課題を専門家が分析し、仮説を提示、その結果を現場にフィードバックし、さらに新たな研究へとつなげていく産学連携の循環が求められているように感じていました。
そもそも、「日本酒学」という言葉が生まれたこと自体、学術と酒類産業を結びつけるひとつの象徴的な試みだと言うこともできるかもしれません。しかし、これを実際に機能させていくためには、大学側の取り組みに加え、産業側の能動的な関与・協力が欠かせません。
新潟大学においては日本酒学はパッケージ型の学問であり、農学や経済学といった単一の学問分野を専門とする研究者が日本酒について研究する方式を掲げています。しかし、その研究においては日本酒およびその産業構造への深い知識が不可欠です。
たとえば「日本酒のデザイン」というテーマで酒蔵を対象としたフィールドワークをおこなうときに、インタビュー対象として最も相応しい酒蔵はどこなのか。「酒蔵の経営」というテーマで蔵元の目指す酒質について調べているときに、「カプロン酸エチルではなく酢酸イソアミルを主体とした香りにしたい」と言われ、その意味するところを理解することはできるのか。酒販コーナーに並ぶ日本酒のラインナップを見て、それがどのような流通経路をたどってきたのかを推測できるかどうか──そのような産業知識の有無は、研究の質に大きく関わってくるはずです。
産業理解が欠如していると、たとえその学問分野の論文としては優れていても、アカデミアの自己満足で終わってしまい、現状をうまく把握できていなかったり、現場での応用にはつながらなかったりといった事態になりかねません。しかし、日本酒産業はもともと閉鎖的で、神秘性を保とうとしていた歴史が長かった側面があります。近年はオンライン上で発言する関係者も増え、情報が手に入れやすくなってきたとはいっても、いまだすべてを把握しきれない複雑性があることも事実でしょう。
こうした事態を解決するためには、産業の現場に立つ人たちが積極的に研究の領域へ踏み込み、課題を共有し、人的ネットワークを駆使して調査を進めていくことが大きな一助となるはずです。実際に業界に関わる多様な立場の人々が、現場の課題を打ち明け、実践的な知を提供する。それを受けて、アカデミアが体系化・理論化された普遍性の高い知を還元する。そうした知の往還が可能になってこそ、日本酒学は真に産業と結びついた、持続可能な学問領域として発展していくのではないでしょうか。
まとめ
日本酒を対象とする学問が持続的に発展し、実社会に貢献していくために、現在、各大学機関では人文社会科学の視点を取り入れた研究や、学問分野を横断する複合的なアプローチが始まっています。そこに加えて必要になってくるのが、現場の実態を俯瞰的に捉える視点です。
研究者と現場の担い手が対話を重ね、課題を共有し、知と経験を循環させていく。そうした営みを通じて、日本酒学は、日本が誇る文化・産業である日本酒を、次の世代へと着実に受け継いでいくための確固たる地盤となるのです。
【シリーズ】学問領域としての日本酒
前編:なぜ、いま“日本酒学”が全国の大学で増えているのか:学問領域としての日本酒
後編:日本酒の未来につながる“知”とは?:学問領域としての日本酒
Pickup記事
2021.10.27
話題の記事
人気の記事
2020.06.10
最新の記事
2026.02.17
2026.02.10
2026.01.27


















