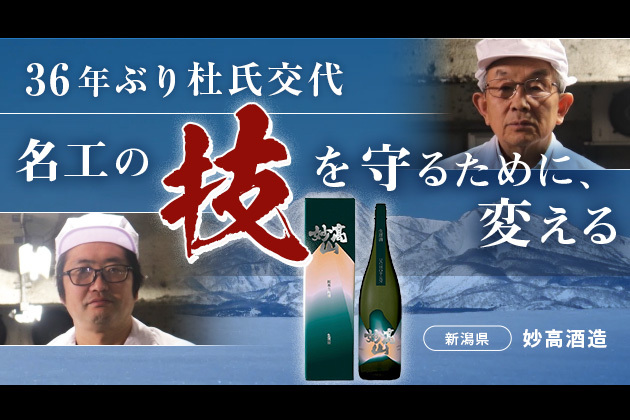2025.02
11
10分の1の規模で再スタート。ヒット商品「じょっぱり」から小仕込みの「杜來」へ - 青森県・六花酒造
1970年代半ばに本醸造酒の「じょっぱり」が全国的な大ヒットとなり、青森を代表する酒蔵の地位を固めた青森・六花酒造が大胆な転換に踏み切りました。本醸造酒・普通酒主体だった蔵の醸造設備を、移転によって約10分の1に圧縮。蔵の柱だった本醸造酒を終売し、小仕込み全量吟醸造りの純米酒蔵として、特約店流通を主体にするという180度の大転換を決断しました。青森県の蔵を訪れ、その背景に迫りました。
「じょっぱり」で名を馳せるも需要低迷で苦境に
六花酒造は、青森県弘前市の人気の銘柄を持つ有力酒蔵3社が合併し、1972年に誕生しました。 灘や伏見の大手メーカーとの競争にも太刀打ちできるように、生産設備を集約してコストを下げることが主目的で、翌1973年に市に生産能力が30,000石の巨大な醸造蔵を建設しました。
コスト競争力により大手を迎え撃つだけでなく、大都市圏に向けてお酒を売り出すため、首都圏の酒類卸と相談しながら1975年にデビューしたのが本醸造酒「じょっぱり」 でした。それまで青森の酒といえばおしなべて甘口だったものを、旨味が主体の辛口タイプに。地元で人気の温湯(ぬるゆ)こけしの腹に描かれただるまを題材にした鮮烈な赤色のラベルデザインが消費者の目に止まり、短期間で大ヒット商品になりました。たちまち、六花酒造といえば「じょっぱり」と言われるようになったのです。
しかし、「じょっぱり」のヒットがあったとはいえ、日本酒全体の需要は1973年のオイルショック以降、下降線に入っていました。特に落ち込みの目立つ本醸造酒や普通酒を主戦力にしていた六花酒造では、新蔵完成直後の22,000石をピークに醸造量の減少が続きました。
1998年に初めて株主ではない一般社員から社長に抜擢された北村裕志さんは、長年営業畑にいたこともあり、販売のテコ入れに力を尽くします。しかし、キャンペーンを打っても効果は長続きせず、販売競争に巻き込まれて、「じょっぱりは安価な酒」というネガティブなイメージが広がってしまいました。
さらに30年以上が経過して蔵の老朽化が進み、機器の故障が頻発。 一方で組織は旧態依然の体制で、社員の仕事の効率化ができず、「毎年売り上げが減っても、経費の削減に限界があり、経営的にはますます苦しい状況でした」と北村社長は振り返ります。
生き残るために付加価値の高い酒造りを目指す
1997年に入社し、2006年に杜氏になった河合貴弘さんは、「安価な酒のイメージを払拭するには、過去に一度も取れていない全国新酒鑑評会で賞を取ることがまず必要だ」と考え、小仕込みができる設備を充実させ、高品質の酒造りに取り組みました。成果が現れたのは7年後の2013BY。全国新酒鑑評会で初めて金賞を獲得しました。翌年も金賞を受賞し、「六花酒造も美味しい酒を造れる」という評判が地元に広がります。
しかし、「評価は市販酒にフィードバックして初めて意味があるものです。20,000リットルのタンクで総米4トンの仕込みでは醪の温度管理は思うように行かないし、一度に大量の麹造りではキメの細かな仕上がりは望めない。酒質勝負で生き残るには、仕込みのサイズを大幅に圧縮するべきだと考えるようになりました」と河合さん。
県内の酒蔵が小仕込みで造った日本酒を特約店限定で流通させて成功していることも刺激になり、今の生産規模を維持するための設備更新か、付加価値の高い特定名称酒に絞った小仕込み蔵にダウンサイジングするかの分岐点に立たされるにあたり、北村社長も後者へと気持ちを固めていきました。
そこに起きたのが新型コロナウイルス感染症のまん延でした。それまでかろうじて差引ゼロの収支で続けてきたものが、一気に苦境に。しかし、蔵には借入金の負担もあって、新天地に新しい蔵を建設するには、蔵の広大な土地(35,000平方メートル)の売先を探す必要がありました。その目処が立たないままいたずらに時間が過ぎていきましたが、2022年に入ると、ホームセンターの大手企業が弘前市への新規出店の候補地として六花酒造の土地に着目。
「それまではいろいろな規制で売却は厳しいと言われていたのが一気に動き出して、あっという間に交渉がまとまりました」と北村社長。こうして、2022年末に酒造りを終えた後、土地を売却することになったのです。
四季醸造の全量純米酒蔵を建設
資金の手当てもつき、ここからは新蔵計画も一気呵成に動き出しました。建設地には、以前から「移るんだったらここが良い」と北村社長が考えていた岩木山の麓の土地を確保。設備面では、旧蔵では総米4トン、20,000リットルの仕込みタンクだったものを、総米600~700kg、仕込みタンクは10分の1の2,000リットルに縮小。洗米も10kg単位とし、搾りは手間をかけやわらかな酒質を実現する槽(ふね)搾りに切り替えました。
火入れ後は急速急冷をして、全量を瓶貯蔵。醸造棟は空調を完備し、四季醸造によって1本1本の仕込みをより丁寧に造れる体制を整えました。醸造能力は最大700石 と、一般的な銘酒蔵並みに落ち着きました。
造るお酒は全量吟醸造りの純米酒に限り、醸造アルコール添加の日本酒は終売することにしました。 新しい蔵でも「じょっぱり」を存続させることも検討しましたが、「まったく新しい蔵へと変身を果たすのだから、蔵の結束力を強めたい。それにふさわしい銘柄が必要だ」(北村社長)と、一時封印することを決意。新しいブランドを立ち上げるべく社内公募を実施し、全社員の投票で「杜來(とらい)」を選抜。2023年夏に新蔵が完成し、10月から新酒を発売して、新生・六花酒造の誕生を宣言したのでした。
新しい蔵での酒造りは、お酒に新しい設備の素材の匂いがつかないよう神経を使ったそうですが、「一番最初にできた純米酒を全社員で試飲した時のみんなの笑顔は忘れられません」と河合杜氏が話すように、飲み手からも「美味しい」という声がたくさん集まりました。
「杜來」が目指すのは吟醸造りで、河合さんは「最初に口に含んだ瞬間の『うまい』という印象を最も大事にしたい。そのうえで綺麗な甘味とキレを重視して、杜來ならではの個性を造っていきます」と説明します。
根強いファンの声に「じょっぱり」も復活
「杜來」は順調な滑り出しになったものの、一方で、「なんで『じょっぱり』を止めてしまったんだ」という苦情の声も予想以上の多さでした。新しい蔵には直売所がありますが、「じょっぱり」が売っていると思って訪れる客も少なくなく、北村社長も直接、「じょっぱり」の終売を惜しむ声を聞かされて心を動かされます。
「本来は、数年に一度、『じょっぱり』を復刻版のような限定商品として出すつもりはありましたが、これだけ『じょっぱり』を求めるお客が多いのなら、リニューアルの形でもう一度復活させてもいいかなと気持ちが変りました 」(北村社長)
かくして、生まれ変わった「じょっぱり」が2024年12月に発売されました。本醸造酒ではなく、60%精米の特別純米酒になり、表記も「JOPPARI」に変えました。
「昔の『じょっぱり』と基本の味は変わりませんが、さらに洗練された酒質になりました」と説明するように、麹と酵母は以前と同じものを使いながらも、より丁寧に麹を造り、小さなタンクで繊細な醪の温度管理をすることで、透明感のある旨味が主体の辛口酒に仕上げています。
使用する米は酒造好適米を使う「杜來」と異なり一般米を使うことで、手頃な価格(税抜き1.8L2,800円)を実現しました。「杜來」が全国の特約店経由主体で流通するのに対し、「JOPPARI」は県内外の問屋経由で広く酒販店やスーパーなどにも並ぶように計画しています。
結果論とはいえ、2ブランド体制で運営することになった六花酒造。北村社長は、「長年、営業の力で酒を販売してきましたが、酒質を追求する全量純米酒蔵となれば、営業主導ではうまく行きません。酒造りのことを熟知した人間が主導する会社へと体質転換しなければ、今回の変身は成功しないと思います」と組織の改革にも意欲をみせていす。
需要が減り続ける本醸造酒や普通酒を見切り、全量純米酒蔵として活路を見出そうとする蔵が増えている現在、特約店確保は熾烈を極めることは確実です。六花酒造がそんな競争に打ち勝てるか、真価が問われる数年になりそうです。
酒蔵情報
六花酒造
住所:青森県弘前市宮地字川添77-5
電話番号:0172-88-7280
創業:1719年(合併前の一社の高嶋屋酒造)
社長:北村裕志
杜氏:河合貴弘
Webサイト:https://www.rokkashuzo.com/
Pickup記事
2021.10.27
話題の記事
人気の記事
2020.06.10
最新の記事
2026.01.27