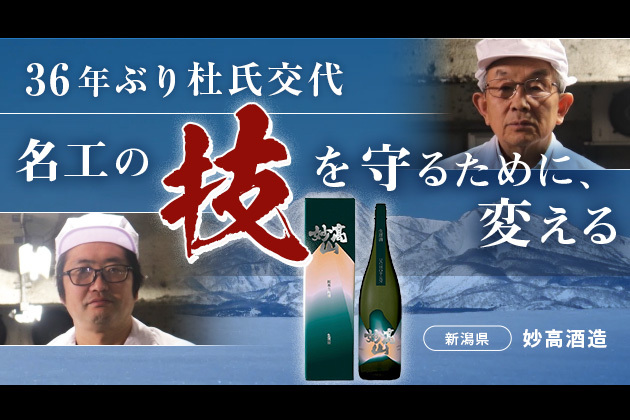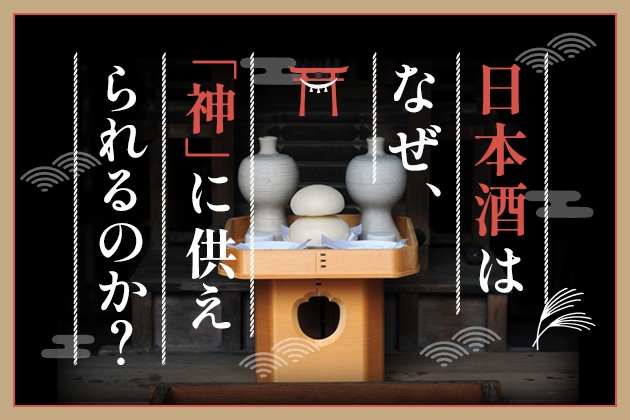
2025.10
28
なぜ、神様に日本酒を供えるの?民俗学者・神崎宣武に聞く日本酒と信仰の歴史
神社や神棚に、「御神酒(おみき)」と呼ばれる日本酒が供えられているのを見たことはありますか? 「御神酒あがらぬ神はなし(御神酒を飲まない神はいない)」という言い伝えがあるほど、日本では神様とお酒に深い関係があるとされてきました。
しかし、この「神」とはいったいどんな神様なのでしょうか。そもそも、なぜ日本では神事で日本酒を捧げる慣習が誕生したのでしょうか。日本全国の村の文化をフィールドワークで探究してきた民俗学者であり神主でもある神崎宣武さんに、日本酒と信仰の関係とその歴史についてお話を聞きました。
神崎宣武(かんざき・のりたけ)
1944年生まれ、岡山県出身。武蔵野美術大学在学中より「忘れられた日本人」で知られる民俗学者・宮本常一に師事。全国の村をまわり、失われてゆく地方の文化をフィールドワークを通して研究・記録してきた。郷里の吉備高原では神主を務める。近著に『社をもたない神々』(角川選書)、『日本人の原風景』(講談社学術文庫)、『「まじない」の民俗』(吉川弘文館)がある。
インタビュアー:Saki Kimura(SAKEジャーナリスト)
ヤマタノオロチを退治した「やしおりの酒」は日本酒なのか?
──神崎先生は、日本全国のさまざまな地域を訪れ、文献として残されてこなかった各地の文化を調査してきた方です。まず、日本には神道や仏教などの思想がありますが、古来から日本人がお酒を供えてきたのはいったいなんの神様なんでしょうか?
神崎さん:そもそもの原点は、宗教というよりもアニミズムです。これは、山や岩など自然界のすべてに霊が宿るという考え方で、世界中に古くからある思想です。
私たちは、困ったときは「神頼み」をしますよね。昔の日本人もそうで、「どんなものにでも神様は宿っている」という考え方をしていました。雨を降らせてほしいときに、水の神である「龍神」にお願いをする「雨乞い」もその流れのひとつです。
──そうした考えが、お酒と結びつくようになったのはいつごろなのでしょうか?
神崎さん:現在の考古学では、縄文時代晩期の日本ではすでにかなりの水田が営まれていたと考えられています。稲作には少なくとも3000年の歴史があり、米のお酒もそのころから造られていた可能性はあります。
日本で最初に造られたお酒として文献に残っているのは、古事記(712年編纂)に書かれている、スサノオノミコトがヤマタノオロチを退治するのに使った 「やしおりの酒」 のエピソードです。やしおりの酒は漢字で「八塩折之酒」 と書きますが、この「塩折」は「しぼり」の当て字であると考えられます。つまり、 「やしおり」とは「たくさん(8回)搾る」という意味なんです。
島根県出雲市にある松尾神社は、かつては「佐香(さか)神社」と呼ばれていました。その名のとおり、酒造の神を祀った神社であり、ヤマタノオロチの退治に使われたとされるやしおりの酒が伝統的に造られ、秋の例大祭で振る舞われています。
私も何度かお邪魔したことがあるのですが、神事としての酒造りは見せてはもらえません。蒸米と麹を合わせて発酵させ、そこに再び蒸米と麹を加えて発酵させるという方法をとられているのでしょう。これを何度も繰り返すうちに、最終的に本当にアルコール度数が15度くらいの濁酒(どぶろく)ができあがるんです。
──なるほど、「しぼる」というのは現代の酒造りでいう「仕込む」のような意味合いで、どんどん発酵させるために何度も原料を加えるということなんですね。
神崎さん:自然の力によって、米だけでこうした酒を造れること考えると、ヤマタノオロチのころから濁酒ながら強酒(こわざけ/アルコール度数が高い酒)が造られていたという説は信じるに足ると思います。
お酒が神様に捧げるごちそうである理由
──日本のアニミズムは、歴史を経て「神道」という形に変化し、「八百万(やおよろず)の神」などという言葉が生まれました。そこでお酒が捧げられるようになったのはなぜなのでしょうか。
神崎さん:かつての日本において、米とは最も価値が高いものでした。江戸時代の石高制(米の生産量=石高によって収入や格式を決める制度)を考えるとわかりやすいかと思います。米を常食できるのは町場などのわずかな人たちだけで、ほとんどの人々は祭事などの特別なときにしか食べられなかったのです。
酒とは、日常的には使えない米に、普段はかけない手間をかけて作るもの。だから、最上のごちそうとして神に供えられるものだったんです。神に供える食事を「神饌(しんせん)」といいますが、最上段に置かれるのは酒、餅、白飯の3点が基本でした。
──確かに、お餅もお酒と同じで「日常的には使えない米に、普段はかけない手間をかけて」作るものですね。
神崎さん:神饌には「今年はこれだけのものが収穫できました。来年もお願いします」とサンプルとして生のまま飾る「生饌(せいせん)」と、調理された「熟撰(じゅくせん)」があります。儀式のあと、この熟撰を下げてみんなでお酒とともにいただくことを、神人供食、または相嘗(あいなめ)といいます。今に伝わる言葉では直会(なおらい)です。
建前としては神と人間が一緒に食事をするという行為であり、実質的には共同体の人間同士の結束を強めるためのならわしでした。
──現代でも、職場に新しい人が入ってきたときや、仕事相手と懇親を深めたいときは飲み会をしますよね。お酒を介して人と親交を深めるというのが、日本人ならではのやり方なのかもしれません。
年間100万樽の酒が消費される江戸の街
──しかし、歴史的な文献に「酒」と書かれていても、いまの日本酒と同じようなものとは限らないのではないかと思います。佐香神社で再現されるやしおりの酒はいまの日本酒と度数が同じくらいだといいますが、その製法が確立されたのはもっと後のことではないでしょうか。
神崎さん: 文献を読み解くときに、 「その言語がどの時代での共通認識となっているか」 を見極めるのは重要なことです。現代に近い清酒造りが生まれたのは織田信長のころ(室町時代)で、奈良の正暦寺という僧院で行われた並行複発酵が基盤になっています。それまでは蒸米と麹を練り合わせた醴(あまざけ※)や濁酒でしたが、ここで「酛(もと)」という仕組みが生まれたんです。
※現代の「甘酒」はアルコール度数を含まないものを言うが、ここでいう「醴」はアルコールを含んだ初期段階のどぶろくのようなものを指す。
──室町時代後期の「酒」と、それまでの「酒」は別のものを指しているということですね。
神崎さん:麹が甘くし、酛が辛くする。甘いと辛いが一緒になってアルコールができるという、並行複発酵の仕組みができたのがこのころです。正暦寺から信長に献上したと思われる記述もあり、信長が「こんなにきれいで旨い酒ができるのか」と感激したと『多聞院日記』に記されています。
ちなみに、このころは醴や濁酒を「白酒(しろき)」、清酒を「黒酒(くろき)」と呼んでいました。黒が水を象徴するとは五行思想からでしょう。透明できれいな水は、底が深いところでは黒く見えることに由来があるのです。
神崎さん:清酒が量産できるようになったのは、江戸幕府の政策によるものです。この時代の灘五郷の酒造りについては、関西学院大学にいらした柚木学先生が詳しく考察されていますね。
このころ、江戸では年間100万樽もの酒が消費されていたそうです。それが、灘から船で運ばれました。江戸中期の人口がほぼ100万人と言われていますから、そのうち半分が飲酒人口だとして、一人あたり年間2樽、一升瓶で80本飲んでいた計算になります。酒が飲めるということ自体が、江戸の都市文化の象徴でもあったわけです。
──江戸の人々がお酒を習慣的に飲むようになったということですが、そのころの飲酒はそれまでのように“神に捧げる貴重なもの”ではなかったのでしょうか?
神崎さん:いえ、江戸時代でも、多くの人にとって酒は日常的には飲めないものでした。米を常食していたのは城下町の武士や商人など、全人口の2割ほど。農民を含める8割の人口は特別なときにしか米を食べられなかったし、酒も飲めませんでした。江戸幕府も、江戸の中期ごろまでは酒が飲める区域を夜間の吉原周辺に留めていましたし、その後の都市計画のもとで神田・日本橋や隅田川沿いにも料亭が並ぶようになりました。江戸の酒文化とは、あくまでも外飲形態で日常生活と切り分けられた形で栄えていったんです。
つまり、清酒醸造はありましたが、町にしろ村にしろ、飲酒は非日常の祝い酒や外飲の酒であったといえます。
明治政府が酒飲みを作った?
──日常的にお酒を飲めていたのは全体の2割ほどとのことですが、農民は自家用に濁酒を造ったりしなかったのでしょうか?
神崎さん:米の無駄遣いになるので造っていません。酔っぱらうためにお酒を飲むようになったのは比較的最近のことで、酒造りは祭りや祝いごとに限られていました。
江戸時代には、江戸の周辺や全国の城下町でも酒蔵が誕生しましたが、全国に広がるのは明治時代に鉄道ができ、酒樽を水路以外で運べるようになってからです。しかし、明治になって国家神道(※)が成立すると、民間のさまざまな歴史を持つ神社が統合され、神社の格式や祭神までが変えられるところもありました。
※国家神道:国力の強化のために神社神道と皇室神道を結びつけ、国民に天皇崇拝と神社信仰を義務付けた制度。
──それぞれの神社で祀られていた神様を、別の神様に置き換えてしまったら、その神社にあった信仰や儀式なども変わってしまいそうです。では、祭事だけではなく日常でお酒を飲むようになったのもそのころからなのでしょうか?
神崎さん:全国的に、飲酒の機会が広がっていきました。たとえば、他国と戦うために徴兵令が導入されましたが、徴兵された人々の結束を図るひとつの手段となったのが酒なんです。
──そんなところでも、お酒は人々を結束させるために使われたんですね。戦争へ向かう恐ろしさを酔いで紛らわしていたのかもしれませんが……。
神崎さん:たとえば、広島市近辺はこのころ陸・海軍の拠点が集中し軍需都市化が進んでおり、酒蔵も発展していきました。全国的にも、軍隊で酒の味を覚えた兵士たちが戦争から戻るのに合わせるように、あちこちの街や村に酒蔵が生まれました。そう考えると、明治時代が酒飲みを作った、ということもできるかもしれませんね。
酒の「清め」機能は世界共通
──お酒と神事の関係性、そしてそれが時代によって変化してきたことがよくわかりました。ところで、日本酒にまつわる文献を読んでいたときに、お酒に酔って「トランス状態」になることが、神とつながる行為だと考えられたという記述を見かけたことがあります。そうした考え方は実際にあったのでしょうか?
神崎さん:個人的には聞いたことがないですが、シャーマニズムの世界ですね。女性のほうがそうした「神がかり」的な力を持つ人が多いといわれています。でも、そこに酒は介在しないのではないでしょうか。
私は神主として座神楽(※)を執り行いますが、途中でトイレに立つわけにはいかないので、その日は朝にお茶を一杯だけ飲むだけになります。水気を取らず、満腹でもない状態になると、神楽の途中で体が宙に浮くような感覚になるんですよね。修験道も修行によって自分の体を追い込むことで、そうした感覚に達するといいます。これも、酒とは別のトランス状態ですね。
※座神楽:神前に奉納される「神楽」の一種で、一人で祈禱をおこなう。
──追い込まれることで不思議な感覚になるのを、神と通じた状態とも解釈できるんですね。社会学者の中根千枝は「酒と社会」の中で、宗教儀礼にはどの国でも酒か動物の血が用いられていると書いていましたが、お酒が神様とつながる手段と考えるのは世界共通なのでしょうか。
神崎さん:酒が「清め」に使われるという点では、世界的につながるでしょう。日本では子供が生まれると産湯(うぶゆ)を使いますが、かつてはそこに酒と塩を入れていました。キリスト教社会では1歳になった子を教会へ連れて行き、赤ワインに足をつける儀礼があります。山岳信仰では、山に入るときに酒で道を清めるという考え方があり、これは東南アジアの山岳地帯でも共通して見られる現象です。
──お酒を浄化と結びつける考え方は、世界各地にあったんですね。世界でバラバラに生まれた宗教やお酒にどうして共通点が生まれるのか、まだまだ解明されていないことはたくさんありそうです。
神崎先生は、日本各地でもはや人々の頭の中にしか残っていないような物語を拾い集め、文献化してこられましたが、その一端をお聞きしながら、日本酒と信仰や宗教の関係を少しでも体系化できたように思います。先生、今日はどうもありがとうございました。
まとめ
神崎さんのお話から、お米で作られた日本酒が神前に供えられるのは、それがかつての日本人にとって最大のごちそうだったからということがわかりました。一方で、明治時代の国家神道の形成により、かつての慣習とは断絶してしまった部分もあるようです。
神道や仏教といった日本の信仰は、時代の流れで統合されることはあったものの、地方によってかつての形を残したまま続いているケースもあります。地元の神社などがどんなふうにお酒と神様をひもづけてきたか、地元の酒蔵がどのようなところに御神酒を供えているか。普段とは違う角度で日本酒を見てみると、これまで知らなかったルーツや魅力を発見できるかもしれません。
参考文献
- 沢の鶴株式会社 酒みづき編集部「日本酒の起源はいつ?日本酒文化の歴史と変遷を紐解いてみよう」
- 国税庁「日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り 調査報告:2 日本酒の歴史」
Pickup記事
2021.10.27
話題の記事
人気の記事
2020.06.10
最新の記事
2026.01.27