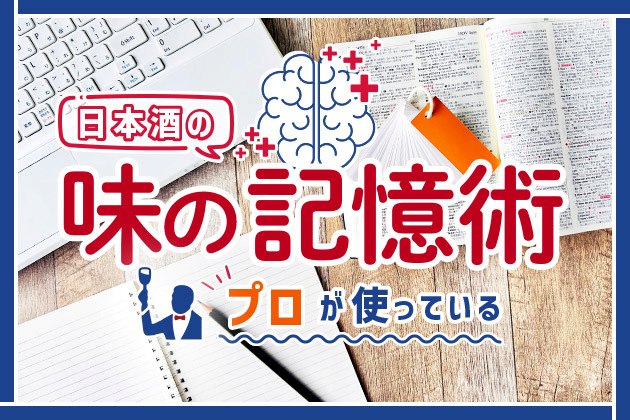
2025.09
09
日本酒の味は言葉じゃなくて◯◯で覚える!プロが教える「味の記憶術」
複数のお酒の味の違いを覚えておくのはなかなか難しいもの。例えば、同じブランドの純米大吟醸と純米酒であればまだ説明しやすいかもしれませんが、「フルーティな香りの純米吟醸3種類」など、似たようなスペックのお酒の繊細な違いを説明するのは至難の技です。
酒販店や居酒屋など、日本酒を扱う仕事をしている人はお客さんから「このお酒はどんな味?」と聞かれることも多いため、それぞれのお酒の個性を伝えるのはいわば必須のスキル。プロは果たしてどんなふうに一本一本のお酒の味わいを覚えているのでしょうか?
今回は、飲食店と酒販店の経験を持ち、「グランド和酒マスターテイスター」の資格を持つ“ぞぬ”さんこと山本聖治さんが、現場で使える記憶術を伝授してくれました。
日本酒の味は、差別化しづらくなってきている
飲食店や酒販店など、お酒を扱う人間の大きな仕事の一つとして、「お酒の味わいを正確に捉え、記憶すること」があります。 お客さんからの「この商品はどんな味ですか?」という質問に適切に答えるために必要なスキルであり、お酒に関わる人間にとっては基礎能力と言ってもいいでしょう。
しかし、昨今の日本酒は、酒質向上のための設備投資やメーカー間の情報共有が活発化したことで、味わいの傾向が似た商品が増え、差別化が難しくなってきているように感じます。
例えばみなさんは、 「マスカットやメロンを思わせる香りがあり、口当たりはなめらかで、後口も爽やかでフルーティーな味わい」 という表現が当てはまる銘柄をどれくらい思いつくでしょうか。少なくとも2つや3つでは済まないはずです。
このような環境に置かれたなかで、どれだけ細かく正確にお酒の味わいを捉えて記憶できるかというのは、お酒に関わるプロとして非常に重要な力になってきます。
私も、過去に勤めていた日本酒専門の飲食店や、現職の酒販店の店頭において、よく「どうやったらそんなにお酒の味を覚えられるんですか?」と質問を受けてきました。これはお酒が好きな多くの人が抱える悩みなのでしょう。
今回はこの「味の記憶法」に焦点を当てて説明します。 慣れてきたらご自身のテイスティングそのものが変わるかもしれません。どうぞお付き合いください。
なぜお酒の味は覚えにくいのか?
そもそも、なぜお酒の味が覚えられないのでしょうか。
この悩みを持つ人の多くは、お酒を飲んだときに、その味を言葉だけで捉えて表現しようとしているという特徴があります。
例えば、「甘い」、「フルーティー」、「マスカット」、「後味スッキリ」、「軽め」というように、そのお酒に対してタグ付けをしていくかのように情報を取り出しています。この言語情報から味わいのイメージを作り上げているのだと思います。
この捉え方の問題は、そもそも人間は言葉の情報を忘れてしまいやすい(※)ということにあります。 誰かと会話をしているときに、人やモノの名前をすぐに思い出せないという経験をしたことはありませんか? 同じように、お酒の味を一旦言葉で覚えたとしても、しばらく経ったら思い出せなくなってしまうことがほとんどです。
言葉で記憶する手法は、長期間の記憶には相性が悪いのです。稀に、「一度人の名前を覚えたら絶対に忘れない」というようなすごい記憶力の持ち主もいますが、そうでない場合は、別の方法で覚えるのがおすすめです。
※「画像優位性効果」といい、心理学者Allan Paivioなどが提唱している。
参考:https://u-site.jp/alertbox/picture-superiority-effect
ぞぬ流お酒の記憶術:味の3Dモデルを作る
では、記憶しやすい味わいの捉え方とはどういうものでしょうか。
それは、「言葉」を当てはめて味わいをイメージすることの逆、言うなれば「味わいを最初に3Dモデルで捉えること」です。先にお酒の味わいを図形で捉え、その後、作成した図形を説明するかのようにテイスティングコメントを作成していくという方法になります。
テイスティングをしながら、その味わいの図形をイメージする
テイスティングをしながら、とらえた特徴を図形に落とし込んでいきます。イメージする要素は以下のとおりです。
・色:果物や穀物など、香りや味に例えられるもののイメージカラーをつける。
(例)マスカットは黄緑、リンゴは赤、熟成香は茶色など・形:口の中に広がる味わいの流れる様子を作る。
(例)淡麗スッキリで余韻が短い→細身で短い形状、濃醇旨口で余韻が長い→幅広な長い形状など・質感:口に含んだ際の舌触りをつける。
(例)舌触りが滑らか→艶のある表面、甘味が多い→柔らかそうに、苦味が強めで引っ掛かりがある→ヤスリのようなザラっとした表面など・濃淡:味わいの濃さを色の透明度で調整する。
(例)味わいが濃密で詰まっている→色を濃くベタ塗りに、あっさりしたりみずみずしさを感じる→色を薄くするなど。
図形で捉えることのメリット
一見すると難しそうに見えるかもしれませんが、この方法には以下のような多くのメリットがあります。
・言葉ではなくイメージ(画像)で記憶するのでお酒の味を忘れにくい。
・テイスティングの速度が格段に上がる。
・テイスティングの精度が上がり、お酒ごとの違いを捉えやすくなる。
・提案力が上がる(このお酒が美味しかったから似ているものを、この味が苦手だったからそうじゃないものを、などに対する提案の解像度が高くなる)。
つまり、3D図形をうまくイメージ出来るようになればなるほど、お酒の味を記憶しやすくなるだけでなく、テイスティング能力も大きく向上するということです。
実際にイメージ図を作ってみよう
例として、冒頭に挙げた「マスカットやメロンを思わせる香りがあり、口当たりはなめらかで、後口も爽やかでフルーティーな味わい」を3Dイメージに落とし込んでみましょう。先ほど挙げた項目に当てはめていくと、以下のようになります。
・色:緑〜黄緑
・形:広がりはあるけどスムーズにしぼんでいく形。重力で落ちる水滴のイメージ。
・質感:ツヤのある表面。なめらかでやわらかそう。
・濃淡:原色に近いがやや淡さのある色。
ちなみにこのイメージをXのGrokでAI生成してみると、こんな図形ができあがりました。
お酒を口に含む瞬間が水滴の下部で、余韻にかけて上部に進んでいくようなイメージです。作ってみて思いましたがもう少し色が淡くても良かったかもしれません。
次は、まったく違うタイプとして、「熟成感がややあるが、まだなめらかといえるほどではなく、力強い酸の効いた無骨な印象の旨辛口」を作ってみましょう。こちらも同様に当てはめていくと以下のようになります。
・色:茶〜黄土色
・形:角ばりがあり、硬さを感じる鋭角で太さのある形
・質感:やすりのようなざらつきがある
・濃淡:透明感は無く、密度の高い色
このイメージをXのGrokでAI生成してみると、こんな図形ができあがりました。
一度このような図形を作って記憶してしまえば、細かい味わいを言葉で覚える必要がなくなるので、記憶できるお酒の特徴のデータ量や思い出すスピードも向上するはずです。
まとめ
今回紹介した手法は日本酒に限らずワインやビール、お酒以外のさまざまな飲料にも活用できます。
ただし、この手法を活用するためには、お酒を味わったときに「この香りや味に似ている」とたとえてコメントできるような、基本的なテイスティング能力が必要です。
日常生活で触れ合ういろいろなものを意識して記憶しながら、お酒を飲んだときに引き出せるようにしておく。その基礎があってこそ、この3Dイメージを上手に作れるようになります。
「日本酒の違いを覚えるのが苦手」「お酒ごとの特徴をうまく捉えられるようになりたい」という人は、ぜひ3D図形を作るテイスティングにトライしてみてくださいね。
Pickup記事
2021.10.27
話題の記事
人気の記事
2020.06.10
最新の記事
2026.02.17
2026.02.10
2026.01.27


















