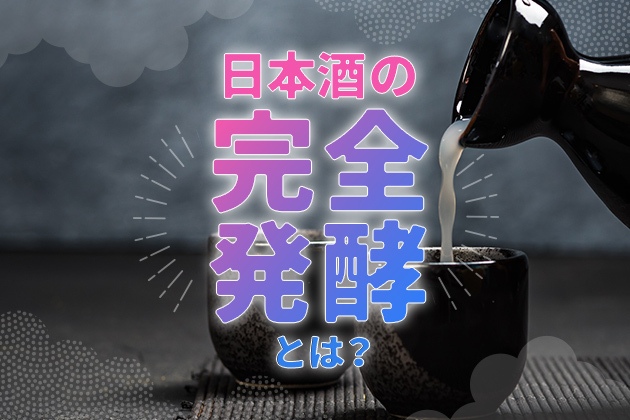2021.09
02
海外で日本酒はまだ「よそもの」。獺祭が目指す現地化とは - 熱量を上げるアメリカSAKE(3)
長年、日本酒の重要な輸出相手国であるだけでなく、現地の酒蔵数でもトップを記録するアメリカ。このシリーズでは、SAKEジャーナリスト・木村咲貴が、アメリカSAKEに関わるプレイヤーの方々にインタビューしながら、その未来の可能性を探っていきます。
第1回目はアメリカ清酒史の第一人者であるきた産業の喜多常夫社長、第2・3回目はアメリカの造り手の同業組合「北米酒造同業組合(Sake Brewers Association of North America)」のウェストン・小西代表にお話を聞きました。最終回となる今回は、アメリカ・ニューヨークに酒蔵を建設中の旭酒造・桜井一宏社長にインタビュー。アメリカ進出の理由や展望、新ブランド「Dassai Blue」の最新情報について伺います!
(※)国税庁の定める「地理的表示」により、『日本酒』と名乗ることができるのは「国内産のお米だけを使い、日本国内で製造された清酒だけ」と規定されているため、この記事では海外で造られたお酒を「SAKE」と表記しています。
輸出でアメリカの市場を知る
──今回はアメリカでの酒蔵建設に関するインタビューなのですが、アメリカと「獺祭」の関係ということで、輸出のお話をしないわけにはいきません。桜井社長は、入社後しばらく輸出事業のためにニューヨークに駐在していらっしゃったんですよね。
桜井:実は私、それまでは輸出反対派だったんですよね。というのも、昔アメリカ旅行をした際に、それなりに有名なホテルのバーで、ひどい味のSAKEカクテルを飲まされまして。「こいつらに味がわかるか!」と(笑)。
さらにニューヨーク駐在を始めたころは、現地のディストリビューター(卸売業者)と取引先を回っていたんですが、これがまたまあ売れない。彼らはほかの銘柄もたくさん扱っているし、メインの商材は日本酒ではなく、お米や海苔、調味料などの食材。本気で取り扱ってもらえるはずがなく、一日かけて十何軒も回っても全然売れないんです。ようやく売れても300mLの小瓶が1ケース出るかどうかという状況で、「いやぁ、桜井さんの真心が通じましたね」なんて言われて(苦笑)。あまり健康的ではありませんでしたね。
──日系大手のディストリビューターは販路が広い一方で、一つひとつのブランドに注力したマーケティングがしづらいというデメリットをよく耳にします。そうした状況から、どうやっていまのようなポジションを獲得したのでしょうか?
桜井:新規の取引先へ売り込みをするのでなく、すでに扱ってくれている取引先でファンを増やしてゆくという方向へ変えたんです。レストランのスタッフ向けの勉強会を行ったり、イベントを開いたり、獺祭を注文してくれたお客さんのテーブルへ行って、私が直接商品の説明をしたりしました。
──ディストリビューターの担当者とではなく、桜井社長がお一人でということですよね。
桜井:はい。こうした活動によってファンになってくれたお客さんたちが、別のお店に行っては「『獺祭』は置いてないの?」と口コミで広めていってくれたんです。ニューヨークは金融都市なので、こうした情報はニューヨークから始まりアメリカのほかの地域やヨーロッパ、香港などに広がっていきました。
──確かに、アメリカは西海岸がよりアジアとの親和性が高いのに対し、東海岸はヨーロッパと強く影響し合っています。
桜井:我々が伸びたのは、海外でもお客さん主導のアプローチを行ったから。当初は反対していた私も、「国境を越えても品質が良ければお客さんはついてきてくれるんだ」と、可能性を感じるようになりました。
日本酒の「現地化」に現地醸造は不可欠
──アメリカ・ニューヨークに酒蔵を建設することになったきっかけは、世界的料理大学「The Culinary Institute of America(CIA)」からのオファーだそうですね。日本食やSAKEのプログラムがある同大学から、学生たちが実際に訪問して学べる酒蔵として誘致の提案があったと。
桜井:日本酒を現地化するためには、誰かが絶対に現地醸造をする必要があると思っていたんです。しかし、CIAからお話をいただくまでは、まさか自分たちがやることになるとは思っていませんでした。「誰かやってくれないかな」とは思っていたので、「あ、自分たちがそのバッターボックスに立つんだ」という感じでしたね。
──いまおっしゃった「現地化」とはどういう意味でしょうか?
桜井:日本酒って、海外にとってはまだ東洋から来た「よそもの」でしかなく、ターゲットの8〜9割は「日本に興味がある」「日本へ行ったことがある」という人なんですよ。そこから踏み出さなければいけないんですが、そのときに引っかかるものがなくてはいけない。現地で造られるような身近なものになると、人々の見る目が変わるはずだと思っています。
──世界的な料理人の卵であるCIAの学生たちが「獺祭」の酒蔵で学ぶことになります。具体的にはどのような取り組みを考えていらっしゃいますか?
桜井:CIAが作ったSAKEのコースはすでにあり、弊社が監修をしていますが、ペアリングを含め、売り方や保存方法、サービスなどを学ぶコースとして設計を進めています。酒蔵が完成したら、酒造りを学生たちに公開するほか、希望者は研修もできます。CIAはニューヨーク観光の目的地のひとつでもありますので、一般の方も見学できるようにする予定です。
──当初は2019年の稼働を予定されていましたが、醸造の許認可や建設などの契約に苦戦し工期が延長したそうですね。アメリカのローカル酒蔵を何軒か取材していますが、みんなその面には苦労しています。しかもそのあと、新型コロナウイルス感染症の拡大により、ニューヨークはロックダウン状態となりました。
桜井:2020年の4月に工事を中断しました。政府からの許可という面では、工事自体を進めることは可能だったのですが、感染症対策をしながら工事や物流を回すのは難易度が高すぎる。たとえ動かしても流通や飲食店が動いていない状況ではどうにもなりませんしね。しかも、その時点での売上は国内・海外ともに前年比40%程度。これは止めるしかないと判断しました。アメリカは状況が落ち着いてきたので、6月から工事を再開予定です。(※)
(※)取材は2021年4月に実施。現在の工事の様子は、旭酒造の公式noteで公開されている。
──2020年5月に行ったオンラインイベントでは、山田錦へのこだわりを貫き、アーカンソー州の農家と契約し、アメリカ国内での栽培を試みているというお話しがありました。
桜井:現在は実験栽培の段階で、稲穂を送ってもらってフィードバックをしながら量を増やしていっています。根の張り方や節目の位置などによって、農薬の与え方、肥料の量、田んぼを落とすタイミングなどが正しいかわかるので、そのあたりのやりとりをし始めているところです。
──ご覧になっていていかがですか?
桜井:まだまだこれからですね。ポテンシャルは大きいのですが、まだしばらくかかると思っています。
──そうすると、初めの方の醸造には日本や他の州のお米を併用することになるのでしょうか?
桜井:そうですね。よい米を使ってよい酒を造るのは最優先なので、序盤は日本からの米もかなりの割合使いますし、ほかの州のものが良ければ使用を躊躇しません。
ただ、基本的にはアーカンソー州の契約農家さんと二人三脚でやっていきたいという気持ちがあります。カリフォルニア州はアメリカ国内では米どころのように言われていますが、毎年山火事が起こるほど水が少ない地域。水が減ったとき、まず優先されるのは人間が飲む水、次は家畜の飲む水、その次は栽培に時間のかかるオレンジなどの多年草の農地なので、一年で枯れていく穀物へ回す水はいちばん後回しになってしまうため、栽培の苦労も大きい。それに比べると、アーカンソーはお米づくりのための安定した条件がそろっているんです。
──発展途上ではあるけれど、期待は大きいということですね。
桜井:農家さんにやる気があるというのが大きいですね。これまでのアメリカのお米づくりは「DNA的に山田錦と認められれば大丈夫」というようなレベルでしたが、同じ山田錦でも生育状況によって品質が違うということを、実例を見せながら伝えて教育しています。親子の農家なんですが、自分たちにとってもよいチャレンジだと燃えてくれていますよ。
アメリカという環境下でできる最高のお酒を
──アメリカへの進出が決まった当初は、現地での流通価格を日本での売価と同じくらいにしたいというお話をしていらっしゃいました。いまはどのように考えていらっしゃいますか?
桜井:日本から輸入された「獺祭」も、現地醸造も、値段はそれほど変わらないんじゃないかと思っています。日本からの輸入品には輸送費用がかかりますが、アメリカ国内の人件費などを考えるとそこまで差は生まれなさそうなんですよね。以前は「獺祭」とは完全に別の商品として、日本酒の入門編のようなブランドに位置付けようと思っていたのですが、だいぶ考えが変わってきましたね。
──いかにも、商品名に「獺祭」という名前をつけないという噂を耳にしたこともありましたが、昨年発表されたブランド名は「Dassai Blue」。「青は藍より出でて藍より青し」ということわざのとおり、従来の「獺祭」を超えるという目標を掲げての命名でした。
桜井:アメリカの原料や環境で価格に見合った最高のお酒を造るという方向に転換しました。結果として、日本産の「獺祭」と食い合いを起こして、どちらかが淘汰されてなくなったとしてもそれはそれでよいと思っています。
──なぜ、そのように考え方が変わっていったのでしょうか?
桜井:理由は二つあります。ひとつは──こちらが大きな理由なのですが──アメリカのブランドを二級品にしても意味がないんですよね。現地のお米や水を使うという条件は違うけれど、トップは目指すべきですし、それに合わせたブランドを作っていくべきだと考えたんです。
もうひとつは、アメリカの酒造りをシミュレーションしていくうちに、安い製品を造ろうとすると、そこそこのものしかできないということがわかったからです。輸入品と価格競争力をつけるマーケット志向ではなく、自信を持っておいしい商品を造りながら、量が増えていくことを加味した価格設定で出していくのが重要だと考え直しました。
──アメリカの「3ティアシステム」は、輸入品であろうと現地醸造であろうとディストリビューターを経由しなければなりませんし、コスト的な意味でそこまで変わらないというのは理解できます。現地醸造酒のディストリビューターは決まっているのでしょうか?
桜井:まだ決まっていません。醸造所にテイスティングルーム付きの販売店を設けるのですが、外へ販売するかはまだ決めていないんです。まずはSAKEが現地に浸透していくための文化を構築すること、そのためによい商品を作るということがいちばん大切なので、それができてから徐々に考えていければと。
──現地の流通事情に直接的に関われるようになることで、品質管理などの面はやりやすくなるのではないでしょうか。
桜井:確かにやりやすくはなるんですが、海外流通の最大の問題は、保存環境や教育システムなど、いろいろなインフラがワインのために整ってしまっていることですよね。例えば、ワインは今年売ることができなくてもヴィンテージがつくことで物によってはさらに高くなっていく。貯めることを前提とした商品構成と、日本酒のフレッシュローテーション前提の商品構成が違うということをワインのディストリビューターに伝えるのに難儀しています。
──ワインを扱ってきた自信と誇りがあるほど、考え方を変えるのは難しいでしょうね。凡庸な例えですが、前職で管理職だった人を中途採用するときのような(笑)。
桜井:「前の会社ではよかったかもしれないけど、ここは違うんだよ?」というね(笑)。最初の1、2年、納得のいくディストリビューターが見つかるまでは、醸造所を訪れるお客さんにしか販売しないというかたちでやっていく可能性はあるだろうと覚悟しています。
なぜ、アメリカでSAKEを作るのか?
──今回、現地醸造のロケーションに選ばれたアメリカですが、世界中に輸出する中で、この国の特徴をどのようにとらえていますか?
桜井:お金と文化、情報発信という観点から、SAKEの浸透具合のバランスがよいと感じています。アジアは日本に近いこともあり、日本から提供された情報を取り込みながら、「日本で流行っているから飲む」という傾向が大きいですよね。アメリカにはワンクッション挟まった情報が流れていくうえ、嗜好品に対して使えるお金がある人も多いので、独自の文化ができあがっていくんです。
──ニューヨークやカリフォルニアの都市部は富裕層も多く、知的好奇心が旺盛で、自分が価値があると信じられるものに投資したい人が多いように見受けられます。ヨーロッパと比べるといかがでしょうか?
桜井:ヨーロッパは、より伝統を大切にする部分もありますし、もうひとつ大きなポイントとして、日本酒事業に関わる現地の人々がヨーロッパの伝統文化に忖度する傾向があるように思います。現地の消費者はもっと新しいものを求めているのに、売り手がワイン文化におもねってしまいがちというか。それに比べると、アメリカは新しいものを受け入れる感受性が比較的強いように思います。マニアックになりすぎず、楽しく探求していくというスタイルが成熟している。これは、アメリカにいる日本酒のプレイヤーのみなさんが努力した結果でしょうね。
──最近、現地の小規模醸造所が増えていることはどのように見ていますか?
桜井:よいことですね。現地の醸造所が増えれば増えるほど、SAKEを身近なアルコールとして捉えてくれる人が増えていきますし、そうでなければ日本酒は世界に広がっていきませんので。一社だけで広めるのはなかなか難しいので、数が増えるのはよいことだと思っています。
──アメリカは世界でも小規模醸造所が最も多いですが、アメリカに酒蔵ができる理由としても、先ほどおっしゃっていた特徴は関係がありそうです。
桜井:新しいものを許容する文化があるのと、クラフトビールによる背景は大きいでしょうね。これからもユニークな蔵が増えていけばよいなと思います。今後は海外で造れば売れるという時代でもなく、市場が成熟するにつれて競争は激しくなっていきますし、覚悟のあるプレイヤーが増えていけばと。
──日本とアメリカでは酒造りにまつわる法律が違いますが、アメリカの現地醸造だからこそやってみたいことなどはありますか?
桜井:たとえばメープルの樹液やホップを使って仕込むみたいなことですよね? やってみて、そっちのほうがおいしいお酒になるならやるでしょうね。本当においしいなら、純米大吟醸やSAKEでさえなく、メープルのお酒しか作らない企業になる可能性だってあります。
──先ほど輸出品と現地醸造が食い合いを起こしてもよいとおっしゃっていますが、お客さんにとって「おいしい」ものがいちばん大切だと考えていらっしゃるということですね。
アメリカの「地酒」になるとは?
──アメリカに日本から輸入された「獺祭」と現地で造られた「Dassai Blue」が並ぶとき、それぞれの役割はどのようになるとお考えですか?
桜井:基本的には、どちらかおいしいほうが残ってほしいと思っているんですよね。例えば「獺祭」は日系のお店に卸し、「Dassai Blue」は現地系のお店という考え方もできますが、そのあたりは自然とできあがっていくものだと思っていますし、現時点で売り先をコントロールするようなことは考えいません。なんでもありですね。
──当初の計画からいままでを見ていても思いますが、お考えが柔軟というか、変化に強いですよね。
桜井:悪く言えば行きあたりばったりなのかもしれませんが(笑)、実際にはそういうものだと思うんですよ。例えばアメリカの日本酒市場なんて、この10年間でずいぶん変わりましたよね。私たちの酒蔵ができあがって浸透していく中でも環境は変わっていくでしょうし、なんでも行けるという方法でやらないと難しいだろうと思うんです。
──「こういうふうにしたい」という明確なビジョンがあるというよりは、桜井社長自身が、どんなお酒ができるかワクワクしていらっしゃる印象を受けます。
桜井:ワクワクしますね。当然、「獺祭」というオリジナルがあって、それをおいしいと思っているメンバーが行って造りますから、そこがスタート地点になるのは確かです。ただ、双子が環境が違うところで育ったら性格が変わっていくのと同じように、その変化は見たいですし、いろいろ試しながら失敗したことも含めて日本にフィードバックしていきたいと思っています。
──「獺祭」は、日本国内でも都市部で有名になりましたが、灘酒がかつて江戸で飲まれるものだったように、「外に出てゆくお酒」というイメージがあります。一方、これからアメリカで造ることでアメリカの「地酒」という立ち位置になっていくわけですが、「地酒」というものについてはどのように考えていますか?
桜井:オリンピック選手みたいなものでしょうか。地元を背負って世界中に出てゆく選手こそが「地酒」であるべきだと思っています。地元でしか飲まれないというのも方法のひとつとしてあるのは理解していますが、海外に出ていき、さまざまなお客さんに出会い、ほかのアルコールとも他流試合をしていくことは、ブランドにも品質にも必要だというのが私たちの考えです。
──「Yamaguchi」という地名は海外のSAKEファンに知れ渡っていますが、旭酒造さんが有名にした部分は大きいでしょう。そういう地酒の役割もあるんですね。
桜井:我々は「出ていくタイプの地酒」ですね。山口という地元を背負い、その地域を誇りに思いながら世界と戦っていくというのが地酒という考えです。アメリカでも、初めはニューヨークですが、ニューヨークを背負ってカリフォルニアやオレゴン、アーカンソーなどの他地域へ広げ、いずれはヨーロッパ、アジアの方に出ていくかもしれません。
輸出を通じて現地醸造の必要性を痛感したという旭酒造・桜井社長。世界中の国々を知る酒造メーカーが語るアメリカの特長は、長い歴史の中でSAKEが造られてきたその風土を浮かび上がらせてくれるものでした。
第1回目では、きた産業の喜多社長とアメリカにおけるSAKE造りの歴史を振り返り、第2・3回目では、SBANA(北米酒造同業組合)とともに、現地醸造の現状と課題を学び、第4回目では、旭酒造・桜井社長と日本の酒蔵の海外進出の展望について考察しました。
WAKAZEの資金調達などでも注目されるアメリカでのSAKE造りですが、世界にSAKEが普及するにあたり、なぜアメリカという国がキーとなるのか、その理由が明らかになった今回のシリーズ。アメリカSAKEの発展は、世界中で日本酒を含むSAKEが飲まれる未来を築くための大きな基盤となるはずです。この連載を通じて興味を持ってくれる人が増えることを願いつつ、その情熱の灯火が絶えることのないよう、これからも注目し、応援し続けられればと思います。
連載:熱量を上げるアメリカSAKE
第一回: きた産業 喜多常夫社長インタビュー 「そのとき、日本酒は役割を果たせるか?」
第二回: 北米酒蔵同業組合(SBANA)代表 ウェストン小西氏インタビュー 前編 「コロナ禍を乗り越え、絆を強めるクラフト酒蔵」
第三回: 北米酒蔵同業組合(SBANA)代表 ウェストン小西氏インタビュー 後編「アメリカの主要都市すべてに酒蔵がある未来へ」
Pickup記事
2021.10.27
話題の記事
人気の記事
2020.06.10
最新の記事
2025.12.09
2025.12.02
2025.11.25